
「レコードの種類と歴史」
トーマス・エジソンが、現在のレコードの
元となった円筒形の記録媒体(上下振動)を
蓄音機とともに発明したのは1877年のことでした。
それから10年後、科学者のエミール・ベルリーナによって、
レコードは円筒形から複製(プレスの)しやすい
円盤形へと発明され、
さまざまな改良と試みがなされて来ました。
その歴史の一部になりますが、以下
それぞれのレコードについて御紹介します。
また、部分的に各記事で取り上げて御紹介することもあります。
★
SPレコード(Standard Playing Record)


円筒形から円盤形になった最初のスタイルで、
蓄音機でかけられたレコードです。
主原料は、シェラックというカイガラムシの分泌するものから
精製した天然の樹脂が一般的ですが、
人工的に作った樹脂や、カーボンなどを合わせた混合物もあります。
クラシックは12インチ(30センチ)、
ポピュラーは10インチ(25センチ)であることが多く、
他にも7インチなど、いくつかのサイズがあります。
材質上、レコード針が音溝を擦る雑音(スクラッチ・ノイズ)が目立ち、
盤は重く、もろくて割れやすいのが欠点です。
回転数は1分間に78回転ですが、時期や会社によっては
80回転だったものもあります。


1925年になると、電気による「吹き込みと再生」が可能になり、
音質は飛躍的に良くなります。
でも、1950年頃までは、まだマスター録音に磁気テープを
使っていない(ラッカー盤を用いている)ため、
編集や加工が出来ず、演奏に失敗すると
始めからやり直さなければならない一発録音の時代でした。
そんなSP盤は、アメリカでは1956年頃に、
日本国内では1963年で製造が中止されています。
復刻CD『モートン・グールドの音楽』(EW-175)や、
『SP盤カフェ』(EW-208) で、SP盤の音の作品をお楽しみになれます。
後者の中に電気吹き込み前の録音が1曲あります。
☆
LPレコード(Long Playing Microgrove Record)

米CBSコロムビアが実用化に成功した
「33と1/3回転」の長時間演奏レコードです。
サイズは、10インチと12インチ。
第二次大戦時に製造研究が進んだ塩化ビニールを
材料に使ったことで、SPレコードに比べて
録音できる周波数が広がり、
レコード針が音溝を擦る雑音も少なくなりました。
また、音溝を細く小さくさせると同時に、
回転数も落としたことで、レコードの収録時間を伸長させています。
1948年6月にアメリカで発表、8月から発売。
日本では、洋楽が1951年3月、邦楽は1953年8月から、
日本コロムビアより国産化されました。
上記、日曜洋画劇場のエンディングで使われていたレコード演奏の
モートン・グールド(Morton Gould)『curtain time』は、復刻CD
『カーテン・タイム』So in Love / 究極のアルバム(VMDT-229)にて
お楽しみいただけます!

☆
EPレコード(Extended Playing Record)

米RCAビクターが1949年2月に発表、
3月から発売した45回転のレコードです。
材質はLPレコードと同じですが、
サイズは7インチ(約17センチ)で、
中央の穴は1インチ半ほどの大きなものになっています。
見た目がドーナツのようなことから、
ドーナツ盤とも呼ばれ、
演奏時間がLPレコードに比べ少ないので、
ポピュラー音楽用に普及しました。


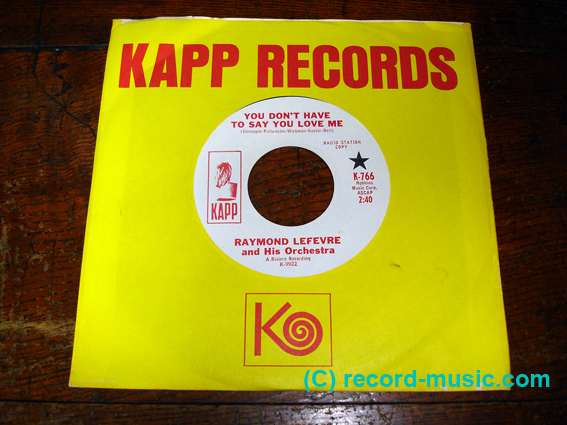
国産の洋楽は1954年5月に日本ビクターから、
邦楽は1954年9月に日本コロムビアより発売されています。
アメリカ盤では、片面2曲が収録され、
厚紙のジャケットが付いているものをEP盤、
片面1曲で絵柄のついたジャケットの無い(袋のみの)ものを
シングル盤として区別することがあります。
また、後に出て来たスタイルですが、LPレコードと
同じ回転数で、7インチのレコードはコンパクト盤と呼ばれます。


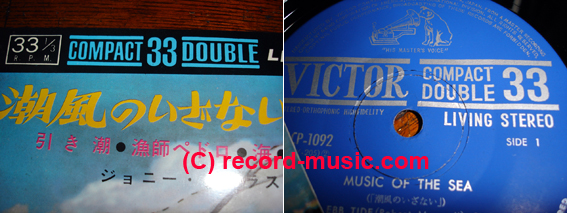
☆
16回転のレコード (16 2/3rpm record)

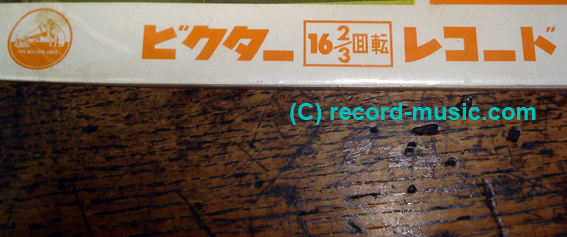
アメリカでは、ちょうどSP盤が
作られなくなって来た1956年頃、SP盤と
入れ替わるように、一時的に出て来たレコードがありました。
それが、16と2/3回転のレコードです。
これはもともと、アメリカのメーカーが考えた、
ある商品がきっかけで作られるようになった規格でしたが、
商品の価格が高かったらしく、
あまり普及しなかったため、短期間で消えてしまったようです。
なお、この商品のためのレコードは、日本で作られていません。
しかしながら、各オーディオ・メーカーが
この回転数でかけられるプレーヤーを作ったため、
本の朗読やドキュメントなど、
あまり音質にこだわらないような内容が収められたレコードが
一般市販されるようになり、それは日本でも
同じように作られていますが・・・当時、そんな回転数の
レコードが日本で発売されていたことを知る方は、
ほとんど、いらっしゃらないようです。
また、アメリカ国内のレストランやオフィス、
スーパーマーケット、ホテル、銀行、工場などで流す、
業務用バック・グラウンド・ミュージックの
長時間(一般市販品でない)レコードでも、
この回転数が使われていました。
その業務用で使われていた16回転のレコードを作っていた会社の音源を復刻CDにさせてもらったのが、『アメリカ国内のレストランやオフィス、工場等で1960年代に流されたバック・グラウンド・ミュージック(シーバーグ編)』(ST-600)です。現在となっては、とても貴重な音源になり、当時のアメリカのムードとしても、そのままをお楽しみいただける逸品です!
☆
ソノシート(シート・レコード)

一般的には、フィルム状の薄いレコードのことを言いますが、
もとはフランスのパリで誕生した「まわる雑誌ソノラマ」に挟まれた
レコードのことです。
「ソノラマ」は、音という意味のラテン語「Sonus」と、
見ものという意味のギリシャ語「Horama」を
合わせたという造語だそうで、
見て読んで聴くというスタイルの雑誌として1959年に登場しました。
写真記事を掲載した冊子状の雑誌の中に、
フィルム状のレコード(ソノシート)が綴じられていて、
ターンテーブルに雑誌ごと乗せてかける訳です。
日本では、歌う雑誌として『KODAMA』が1959年11月に創刊。
朝日新聞が設立した朝日ソノプレス社が、
フランスのソノプレス社と提携した『朝日ソノラマ』は12月に
創刊されました。このソノシートの厚みは0.1ミリです。
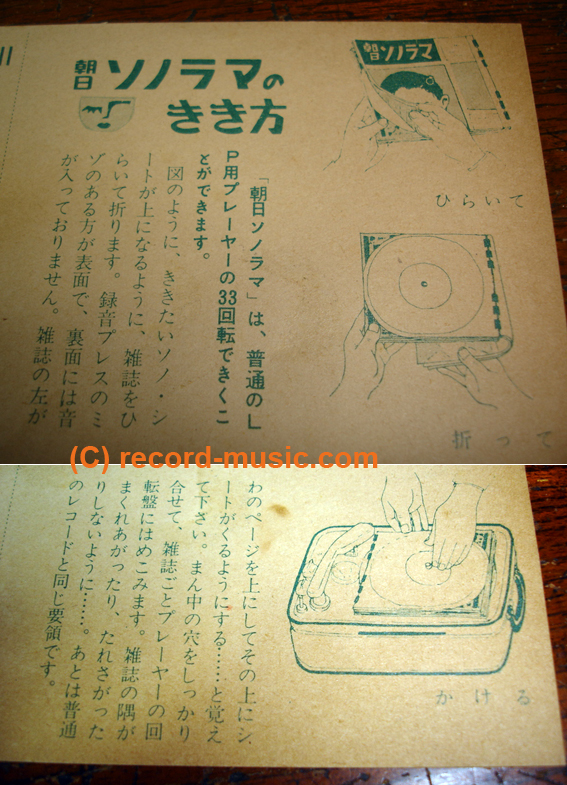



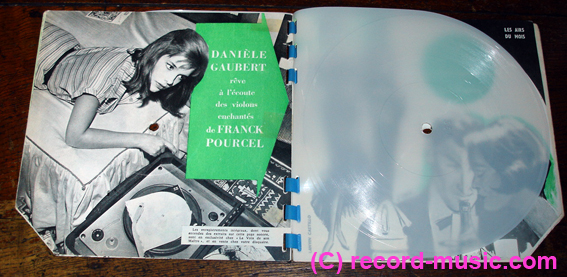
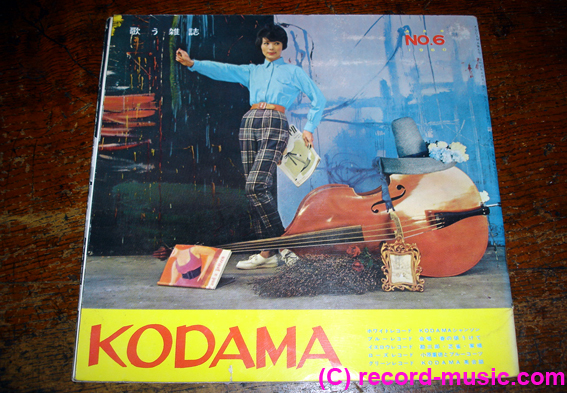
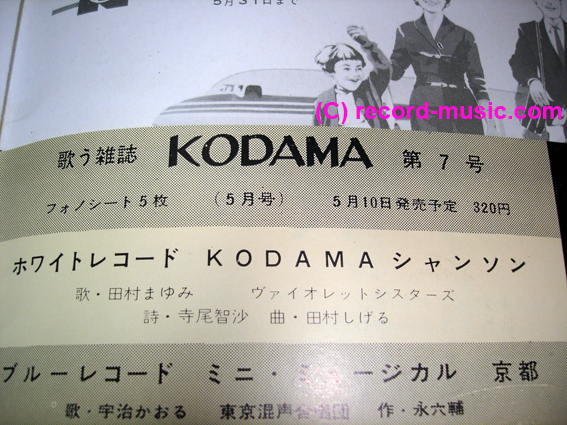
ソノシートは、ふつうのレコード盤よりも安価に作ることが
出来る上、取り扱いも手軽なため、
雑誌やパンフレットなどに挟むものといった、多くの用途に
作られるようになりました。
宣伝配布用の自主制作盤が多く、企業のコマーシャルソングを
吹き込んだものや、冷蔵庫などの家電商品の説明などにも使われています。
また、ソノシートをハガキ状にしたもの等もありました。


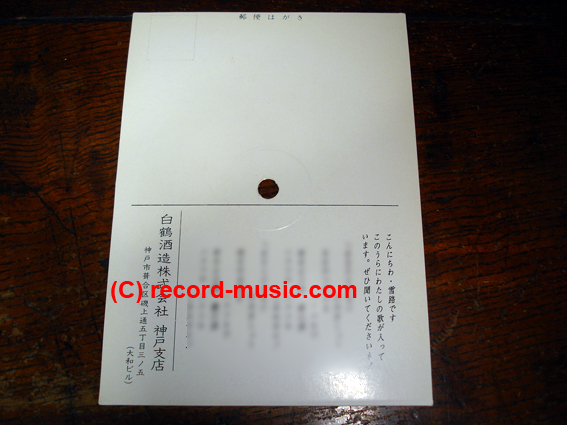
☆
ステレオ・レコード
アメリカでステレオレコードの技術が公開されたのが
1957年の末でした。翌年の1958年からは、アメリカにある
大小の各レコード会社が競って、
LPレコードに「STEREO」の文字を入れ始めるものの、
モノラル録音を単に疑似ステレオ(電気的ステレオ)化
したものだったり、
純粋なステレオ録音ではなく、左右別のトラックに分けただけ
のLPレコードも案外多く出回っていました。
国産洋楽のステレオLPレコードは、
1958年8月に日本ビクターから、
翌月に日本コロムビアから発売されています。




☆
色々なレコードを御紹介する筆者おすすめのCD!
☆
関連する記事として、以下の記事もおすすめします。
© 2023 磯崎英隆 (Hidetaka Isozaki)
